How Stablecoins and Asset Management are
Reshaping Japan’s Digital Economy
To know more Join Us at GFTN Connect @Japan Weeks
21st October 2025 | 09:30am to 05:30pm
with simultaneous Japanese-English interpretation.
.jpg?width=183&height=93&name=noimg%20(4).jpg)

.png?width=238&height=93&name=final%20logo%20Horizontal%20with%20blue%20background%201%20(1).png)

GFTN Connect: Japan Weeks Agenda
Japan Weeks は、2025 年で3 年目を迎える政府支援のイニシアティブであり、日本がグローバル金融ハブとしての役割を高める様子を発信するために設けられました。金融庁による資産運用立国戦略の一環として、10 月の集中期間(10 月20日〜24 日のコア週)に、国際的な投資家や資産運用会社、金融機関が一堂に会し、オルタナティブ投資、サステナブルファイナンス、資産運用政策などについて議論します。プログラムには多数の金融機関主催イベントを特色としています。今年度は、Global Finance and Technology Network(GFTN)Japan が三井住友銀行(SMBC)と共催し、10 月21 日に「GFTN Connect Japan」を開催します。GFTN Connect Japan は、国内外の金融テクノロジー・イノベーションとコラボレーションのためのエコシステム構築を目指す月次型コミュニティ・イベントシリーズです。
Registration
This event has received an overwhelming response and registration is now closed.
If you'd like to join the waitlist, please add your details here: Waitlist Form
Should any slots become available, we’ll notify you via your business email.
Registration
午前の部: ステーブルコインはどう金融システムに影響を及ぼすか?
受付
歓迎の挨拶
FSAによる基調講演
開会挨拶

Keiji Matsunaga
General Manager, Digital Strategy Dept., Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Jeff Hutchins
Head of Japan Equities, Asia Risk Trading, Jefferies

Naoyoshi Shitara
Regional Sales Head, Nucleus Software Japan

David Chan
Managing Director and Partner, Boston Consulting Group
Moderator
クラッシュコース:ステーブルコインの基礎から金融革新まで
本セッションの冒頭では、ステーブルコインの基本的な概念について整理いたします。主な類型、規制環境、具体的な活用事例、そして金融イノベーションを促進する上での役割など、基礎的な事項を概観いたします。また、中央銀行デジタル通貨(CBDC)とステーブルコインとの相違点、およびそれぞれが伝統的金融と分散型金融の領域において果たす機能についても議論いたします。さらに、国際送金や業務効率化といった分野における具体的 な活用事例を紹介するとともに、ステーブルコインに内在するリスクや規制上の課題についても論じます。日本においては、先進的な規制枠組みの整備と、JPYCに代表されるステーブルコインの取り組みにより、制度面・実務の両面で機関投資家による導入が進展しており、デジタル金融および決済インフラの進化を象徴する事例として注目されています。

Prof. Chia Tek Yew
Advisor, National University of Singapore (NUS) & Asian Institute of Digital Finance (AIDF)

Name Here
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form

Name Here
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form

Name Here
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form
パネル1:先駆者たちの競演拡大するステーブルコイン・―エコシステムにおける協調競争
本セッションでは、日本におけるステーブルコイン市場の変化と、グローバル市場における日本のポジショニングに焦点を当てます。JPYCをはじめとする先進的なプロジェクトが、いかにして競争優位性を確立しているのか、その差別化要因を探ります。また、日本独自の規制枠組みが国内のイノベーションをどのように促進しているのか、さらに国内の金融機関やフィンテック企業がグローバルなエコシステムの中でどのような立ち位置を築いているのかについても議論します。ステーブルコインの急速な拡大を支える主要な導入要因、業界内での協業のあり方、そして競争環境の変化が市場に与える影響について、様々な視点から考察を深めてまいります。

Noritaka Okabe
CEO, JPYC

Yo Nakagawa
Senior Executive Director, Monex Group

Kenta Sakakibara
Country Manager for Japan, Circle

Yuki Kamimoto
Chief Executive Officer, CoinDesk Japan
Moderator
パネル2:既存金融機関はステーブルコインにどう向き合うのか
本セッションでは、日本および世界各国の銀行が、ステーブルコインをいかに受け入れ、現代の金融システムの変革に取り組んでいるかを考察します。現在、世界の金融機関の約半数が、24時間対応の国際送金をはじめとする、より迅速かつ効率的な決済手段としてステーブルコインの導入を試行しており、従来の金融インフラは大きな変革の局面を迎えています。こうした動きの中で、競争戦略も急速に進化しつつあります。本パネルでは、ステーブルコイン導入を後押しする要因、業務効率の向上が銀行業務に与える影響、そしてデジタル金融イノベーションの今後の展望について、多角的に議論を深めてまいります。

Naoto Shimoda
General Manager, Digital Strategy Department, SMFG

Jeff Hutchins
Head of Japan Equities, Asia Risk Trading, Jefferies
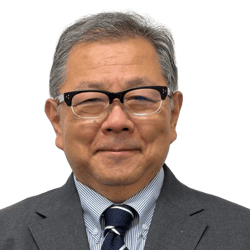
Naoyoshi Shitara
Regional Sales Head, Nucleus Software Japan

David Chan
Managing Director and Partner, Boston Consulting Group
Moderator
パネル3:決済エコシステムの再編:ステーブルコインと既存モデルの交錯
本セッションでは、ステーブルコインが従来のクレジットカード報酬制度および決済インフラに与える影響について検討します。高速かつ低コストの取引、さらにはプログラム可能なデジタルインセンティブの導入により、ステーブルコインは既存の決済モデルに変革をもたらしつつあります。リアルタイム決済の実現や国際送金の効率化といった利点は、VisaやMastercardといった既存プレイヤーに対し、戦略の見直しを迫る要因となっています。特に、日本円建てのステーブルコイン(JPYCを含む)の普及は、国内市場における導入を加速させるとともに、金融機関に対して競争戦略および協業の在り方を再考させる契機となっています。本パネルでは、こうした変化が消費者との関係性、決済経済の構造、そしてイノベーションと既存勢力のバランスにどのような影響を及ぼすのかについて、包括的に議論を深 めてまいります。

Prof. Chia Tek Yew
Advisor, National University of Singapore (NUS) - Asian Institute of Digital Finance (AIDF)

Sunny Wang
Managing Director, OKJ

Oliver Matthew
Head of Institutional Equities, CLSA
Moderator

Name Here
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form
閉会挨拶

Pieter Franken
Co-founder & Director, Japan, Global Finance & Technology Network (GFTN)

Name Here
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form

Name Here
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form

Name Here
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form
受付・ネットワーキング
Yo Nakagawa, Senior Executive Director, Monex Group
Jeff Hutchins, Head of Japan Equities, Asia Risk Trading, Jefferies
Naoyoshi Shitara, Regional Sales Head, Nucleus Software Japan
受付・ネットワーキング : 12:30pm to 01:30pm
午後の部:資産運用のパラダイムシフト
開会挨拶
クラッシュコース:グローバルおよび日本の大規模資産移転北米・アジア太平洋における富裕層の伸長、世代交代による資産の移転、代替投資やデジタル運用の拡大傾向
2024年、世界の富裕層(HNWI:High-Net-Worth Individuals)の資産総額および人口は大きく増加し、特に北米およびアジア太平洋地域が成長を牽引しました。日本においても、株式市場の上昇と円安の影響により、富裕層の資産は8.2%増加しました。今後、2048年までに総額83.5兆米ドルにのぼるとされる世代間の資産移転が、X世代、ミレニアル世代、Z世代といった「次世代富裕層(>Next-gen HNWIs)」へと進む中で、彼らの投資嗜好はオルタナティブ資産やデジタルチャネルでのエンゲージメントへとシフトしています。このような構造変化を踏まえ、資産運用業界は日本を含む世界各国において、次世代顧客との関係構築に向けた戦略の再構築が求められており、今まさに大きな転換点を迎えています。
ファイヤーサイドチャット: "なぜ日本の個人投資家は、すべての貯蓄を株式市場などに移さないのか"
過去10年以上にわたり、「世代を超えた資産移転の津波」が資産運用業界の構造を大きく変えると語られてきました。日本政府もNISAなどの制度を通じて、現預金から投資への資金シフトを促進してきましたが、依然として多くの日本人は、全資産を株式市場に投じるような動きには至っていません。本セッションでは、これまでに見られた資産シフトの背景を振り返るとともに、なぜ日本の一般家庭が、株式、投資信託、FX、暗号資産などのリスク資産への投資に慎重であり続けているのか、その要因を掘り下げます。制度、文化、金融リテラシー、マクロ経済環境など、複数の視点から議論を展開し、今後の資産形成のあり方や、次世代投資家との向き合い方について考察します。
パネル1:"NISA のその先へ 一過性の刺激策から持続可能な―投資文化へ"
制度は、これまで投資経験のなかった個人にとって投資への第一歩を踏み出す契機となり、一定の成果を上げてきました。しかし、真に持続可能な投資文化を育むためには、NISAを超えた制度設計や政策的支援が求められています。税制や資産運用の慣行に対する抜本的な見直しを含め、長期的な投資参加を促進し、より幅広い層の参画を実現するための改革が必要です。また、個人投資家と機関投資家の資本をどのように連携させ、日本の投資環境全体を包括的に変革していくかも重要な論点です。金融リテラシーの向上と安定的な資産形成を両立させるためには、制度面だけでなく、教育や情報提供の在り方も含めた多面的なアプローチが求められます。本セッションでは、NISA制度の限界を踏まえたうえで、この初期的な刺激策を超えて、いかにして日本に根付く投資文化を築いていくかについて、政策、業界、投資家それぞれの視点から議論を深めてまいります。

David Semaya
Executive Chairman & Representative Director, Sumitomo Mitsui Trust Asset Management

Takashi Takamura
President, Japan Country Head, Franklin Templeton

Laurent Depus,
Secretary General, International Bankers Association of Japan
Moderator

Name Here
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form
パネル2: "資産運用の構造変化に、資産保有者はいかに対応しているか"
本セッションでは、日本の年金基金、保険会社、企業年金、大学基金といった資産保有主体が、国内の資産環境の大きな変化にどのように対応しているのかを検討します。特に、投資制限の緩和を含む規制改革、受託者責任を重視する「アセットオーナー原則」の導入、そして長期・分散型の投資戦略への転換といった動きが、資産運用の実務にどのような影響を与えているのかに焦点を当てます。また、日本が「資産運用立国」を目指す中で、ガバナンスの強化、透明性の向上、機関投資家および個人投資家との協働といった観点から、資産運用の在り方をいかに再構築していくべきかについても議論を深めます。こうした進化は、日本の投資ポテンシャルを引き出し、経済の活力を高める鍵となるものであり、制度・実務の両面からの対応が求められています。
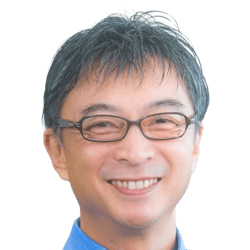
Ken Yasunaga
Founder & Managing Partner, Global Hands-On VC

Bradley Busetto
Vice-Chairman and Co-Founder, SDG Impact Japan

Frank Packard
Partner, Eight Peak Partners
Moderator

Name Here
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form
パネル3: "デジタル・シフト テクノロジーが変える資産運―用の未来 "
本セッションでは、デジタル技術が日本の資産運用業界にもたらす構造的な変化について検討します。規制改革とテクノロジーの進展により、投資業務の柔軟性、運用効率、そしてイノベーションの可能性は飛躍的に高まりつつあります。一方で、既存のレガシーITシステムがもたらす制約や、業界全体がデータドリブンかつアジャイルな運用モデルへと移行する過程で直面する課題も浮き彫りになっています。加えて、富裕層および個人投資家の間では、モバイルアプリ、オンラインポータル、ロボアドバイザーといったシームレスなデジタル体験への需要が急速に高まっており、リアルタイムでのポートフォリオ管理や、オルタナティブ投資への容易なアクセス、透明性の確保が求められています。こうしたデジタル進化は、日本が「資産運用立国」として国際的な地位を確立し、持続可能な成長を実現するための重要な鍵となります。本パネルでは、テクノロジーが資産運用の在り方をどのように再定義し、業界の競争力をいかに高めていくのかについて、多角的に議論を深めてまいります。

Teddy Hung
Principal, Boston Consulting Group

Keiko Sydenham
Co-founder & CEO, LUCA Japan Co.

Prof. Chia Tek Yew
Advisor, National University of Singapore (NUS) - Asian Institute of Digital Finance (AIDF)
Moderator

Name Here
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form
パネル4: "資本の地政学 投資家は米国市場の外へ向かっているのか"
本セッションでは、分散投資の潮流が資本の地理的配置にどのような変化をもたらしているのかを検討します。近年、インド、中国、東南アジアといったダイナミックな成長を遂げる地域に対し、機関投資家の関心が高まりつつあります。日本の投資家による米国資産からの資金移動は限定的ではあるものの、絶対額としては無視できない規模に達しており、分散投資への関心の高まりを示唆しています。こうした動きの背景には、地政学的リスク、貿易摩擦、構造的な市場要因などが複雑に絡み合っています。これらの要因が、グローバルなポートフォリオの再構築を促し、長年にわたり支配的であった米国市場の地位に変化をもたらす可能性もあります。本パネルでは、こうした資本の再配分が新興国市場にどのような機会をもたらすのか、そしてそれが世界の投資地図にどのような再編をもたらすのかについて、多角的に議論を深めてまいります。

Nana Otsuki
Senior Fellow, Pictet Asset Management (Japan) Ltd

Oliver Matthew
Head of Institutional Equities, CLSA

CJ Morrell
Managing Director, Head of Japan, Fiera Capital

Jesper Koll
Expert Director, Japan Catalyst Fund
Moderator
閉会挨拶

Pieter Franken
Co-founder & Director, Japan, Global Finance & Technology Network (GFTN)

Name Here
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form

Name Here
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form

Name Here
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form
促進してきましたが、依然として多くの日本人は、全資産を株式市場に投じるような動きには至っていません。本セッションでは、これまでに見られた資産シフトの背景を振り返るとともに、なぜ日本の一般家庭が、株式、投資信託、FX、暗号資産などのリスク資産への投資に慎重であり続けているのか、その要因を掘り下げます。 制度、文化、金融リテラシー、マクロ経済環境など、複数の視点から議論を展開し、今後の資産形成のあり方や、次世代投資家との向き合い方について考察します。
Laurent Depus, Secretary General, International Bankers Association of Japan
のように対応しているのかを検討します。特に、投資制限の緩和を含む規制改革、受託者責任を重視する「アセットオーナー原
則」の導入、そして長期・分散型の投資戦略への転換といった動きが、資産運用の実務にどのような影響を与えているのかに焦点
を当てます。また、日本が「資産運用立国」を目指す中で、ガバナンスの強化、透明性の向上、機関投資家および個人投資家との協働といった観点から、資産運用の在り方をいかに再構築していくべきかについても議論を深めます。こうした進化は、日本の投資ポテンシャルを引き出し、経済の活力を高める鍵となるものであり、制度・実務の両面からの対応が求められています
いるのか"
Oliver Matthew, Head of Institutional Equities, CLSA
CJ Morrell, Managing Director, Head of Japan, Fiera Capital

